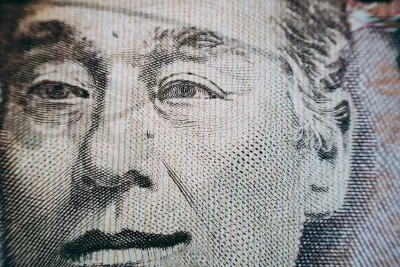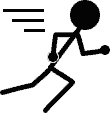どうすりゃ失敗しない?制作会社の選び方
- 公開日:
- 更新日:

ねば損コラムは、サイト制作の現場を熟知している現役のWEBデザイナーが書くコラムです。
この記事では、『サイト制作会社の選び方がわからない』という担当者様に向けて、制作会社選びで失敗しないための4つのポイントを詳しく解説していきます。
要点

『結論をまず言えよ』というのが僕の心情ですので、まず要点を箇条書きした上で順番に詳細を解説していきます。
- 正しい方法で情報収集をする
- 有益な相見積りのやり方
- 目的をはっきりさせる
- 事実に基づいた決断をする
それでは以上4つの要点についてさっそく解説を始めます。
正しい方法で情報収集をする

結論から言えば業界の常識を知ることさえできれば失敗する可能性はかなり減らせます。
しかし、一般の方にとってそれを一瞬で理解するには少しハードルが高いかもしれません。
そこで、まず正しい情報収集の仕方を解説いたします。
エビデンスがある事柄のみを事実として受け取る

情報収集の第一段階はホームページなどの閲覧だと思いますが、そこに記載されている具体的な事柄のみを事実として受け取りましょう。
つまり、抽象的なキャッチコピーやヴィジュアル上の演出などは一旦意識の外に除外してください。重視すべきは、生産能力が測れる以下の事柄です。
実績・料金の目安・どんなサイトが作れるのか・おおままかなプランニングの例・受注から納品までの流れ・制作体制(人的リソース)など、制作体制やメソッドを見ることでその会社のポリシーみたいなものがおぼろげながらも見えてくるはずです。
エビデンスがない情報を過信しない

物事の判断で失敗する要因の1つが、演出上の信頼感を過信して『大丈夫だろう』で進んでしまうことです。はっきり言ってこちらが欲しい情報がWEBや書面などに揃っていない時点でその会社は選択肢から除外して大丈夫です。
なぜかと言うと、書いていないのには何かしら理由があるからです。
例えば以下のような理由です。
- 下請け業務がほとんどのため、元請けとの契約上、実績が掲載できない
- 料金はその都度、客の空気感で決めているから明示できない
- いつも同じようなテンプレートを流用してサイトを作っている
- いつも予算に合わせてそれっぽいサイト構造作っているだけ
- 制作リソースは外注だのみだから掲載できない
- 離職率が高いためリソースが安定しない
WEB業界は割と下請けも孫請けもありありな業界です。
下請け業務を主にしている時点でWEBディレクターとしての本来の能力はどんどん必要なくなっていきますから、WEBディレクターは元請けの会社との営業兼、窓口くらいにしか機能していないはずです。従ってプランニングや工程管理の能力はないと考えた方が妥当です。
また、質が高いものを作らないといけない時に外注のコントロールはひどく困難なものです。特に成果物に対して日常的に質を求めていない会社では、外注のクオリティコントロールなんてまずできないと断言できます。
上記のように様々な理由があり、情報を公表していない可能性がある以上、然るべき情報が開示されるまで”選択肢に入れないこと”が私たちが取れる最も最良の手段です。
”自社のホームページにまで手がまわっていないだけ”という可能性もありますが、情報がないのですから判断のしようがありません。やはり、選択肢に入れないことが最良です。
有益な相見積りのやり方

相見積りをする最大のメリットは、価格を比べられることではありません。
それぞれ何ができて何ができないのか、プランニングの内容や戦略性の違いを比べることができるところです。
かかる料金が高いほどできることが多く、低いほどできることは少なくなります。
まずは高い方から見積りをとっていき、その料金にはどんな調査や戦略性が含まれているのか吟味することでかなり有益な情報収集にもなりますし、最も安いところの見積りと比較してその違いからいろいろと見えてくるものがあるはずです。
戦略性が不要のサイトを作りたい場合は、それこそ無料で作れるツールを探して無料で作るか、FacebookなどのSNSに注力するか、とにかくお金をかけずにやることを推奨します。
目的をはっきりさせる

ちゃんとしたWEBディレクターであればヒアリングすることでお客様の目的を明確化してくれるでしょうが、残念ながらそうでないWEBディレクターもたくさんいます。
目的に優先順位をつけることは何においても重要であり、WEBサイトの制作においてもそれは例外ではありません。
何を第一優先の課題とするのかによってサイトの構造は変わってきます。
そこで社内で抱えている課題をリストアップし、それぞれ優先順位をつけてください。
それは相見積りを出す際に必ず役に立ちます。
WEBディレクターとの打ち合わせの中でWEBサイトで、短期的にできることやできないこと、中長期的にできることなどがわかってくるはずです。
事実に基づいた決断をする

決断において『信頼の演出に流されないこと』と『根拠のない安心を過信しないこと』が何よりも重要です。
言うまでもないことですが、会社と会社も、会社と人も金銭的な損得で繋がっています。
例えば、『付き合いのある会社に紹介してもらった会社だから大丈夫』は、サイトの戦略性や完成度となんら因果関係を持ちません。
なぜかと言うと、その制作会社に頼んだおかげで『問い合わせが明確に増えた』などの実績があり、その上での紹介であれば大いに信頼に値しますが、そうでない限りおそらく紹介特典など、会社同士の利害の一致による紹介であることがほとんどだからです。
そこで得られるものは虚構の安心感のみです。なんら有益ではありません。
ですので、エビデンスがあることは履行可能な事柄として解釈し、エビデンスのない事柄は履行されない事柄として解釈しましょう。
まとめ
まず自社の目的を明確化する。情報はエビデンスがある事柄のみを事実として解釈し、その中で違いを比べて決断する。
文字に起こしてみれば当たり前のことですが、商談相手は信頼感の演出でそれを忘れさせるよう働きかけてきます。
僕の経験上、『こんなことできますか?』という問いに対して、その問いの深堀りやエビデンスを示すのではなく、とりあえず『できます』というような回答を返すWEBディレクターもとい営業マンは、まず信用しない方がいいように思います。
WEB業界は基本的に知識格差を利用した営業が主だと思いますので、こちらは事実のみに着目して比較検討しましょう。
最後に余談ですが、多くの会社経営者が自分の会社を完全にはコントロールできないのと同じように、制作会社もそれは例外ではありません。
相手の会社も割といろんなことがコントロールできていない状態で走っているという事実を忘れなければ営業トークに安易に乗る気も失せるというものです。
制作会社の選び方カテゴリーの他の記事
もっと見る